最近は関わる仕事の難易度が上がったのも理由の一つですが、明確が正解がなかったり、解決策が全く浮かばない時があります。
そんなときにAIを利用して状況整理や案を出してもらうことが増えてきました。
もしAIが無かったらと思うと上手く進められなかった仕事もあるのではないかと考える時もあります。
利用するにあたって気をつけていることをメモします。
・情報のソース
AIに質問した後、本当に正しいものかをジャッジする必要がある場合、
「回答の根拠、統計データ、サイトなどを提示してください」
というように確認を投げています。
AIの回答文だけを鵜呑みにしてしまうのはまだ危険かなと思う時があります。
・個人、会社等を特定できる情報、機密情報を質問に載せない
これが最も気をつけなければならないことかと思います。
AIを利用しないように会社として取り決めしているところもあります。(弊社)
質問する際はしっかりチェックした上で投げたいですね。
まだ公開していない情報などを投げてしまうと情報漏洩につながってしまいます。
文章要約してといって社内機密文書投げるのはもってのほかですね。。。
これは私の疑問なのですが、会議議事録をAIがまとめる機能など見かけますが、
議事の内容を学習に利用されたりするのでしょうかね。。。
そうであるなら結構な情報量が蓄積しているような気がします。
・条件の明確化
「Aって商品使いたいんだけど内容教えて!」
のようなざっくりした質問だと納得いく回答をもらえなかったりします。
例えば
Aという商品導入を考えている
予算はXX円
〇〇のために利用する予定だが、
フィットするものか
また、類似商品等存在するか
という形で前提条件や利用理由を記載すると、いい感じに回答をもらえたりします。
5W1Hを意識するのに似ていますね。
一回の質問でなく、複数回のラリーでもいいので前提を詰めながらAIを利用するのも全然アリだと思っています。
・【重要】Temperatureの設定
意外と知られていないのかもですが、正確な情報欲しいときは設定値を意識するのが良いです。
以下、Gemini 2.5 ProでTemperatureについて質問した際の回答です。
Temperatureとは何か?
AIが文章を生成するとき、次に続く単語の候補を複数考え、それぞれの候補がどれくらい「ありえそうか」を確率で計算します。例えば、「今日の天気は」という文章の後には、「晴れ」「雨」「曇り」などが高い確率で候補に挙がります。
Temperatureは、この確率分布を調整する役割を果たします。
デメリット: 文脈から外れたり、論理が破綻したり、事実ではない情報(ハルシネーション)を生成するリスクが大幅に高まります。
Temperatureが低い(0に近い)場合
AIは、計算された確率が最も高い単語をほぼ必ず選びます。つまり、最も「ありきたり」で「予測可能」な選択をします。
結果:
正確性が高い: 学習データに基づいた、最も可能性の高い事実や情報を出力しやすくなります。
一貫性がある: 同じ質問をすれば、ほぼ同じ回答が返ってきます。
決定的: 出力が固定的で、ブレが少なくなります。
デメリット: 文章が単調になったり、面白みに欠けたり、同じ表現を繰り返したりすることがあります。
Temperatureが高い(1に近い、あるいはそれ以上)場合
AIは、確率が低い意外な単語も積極的に選ぶようになります。確率の差が小さくなり、より多くの単語が選択肢に入るイメージです。
結果:
創造性が高い: 独創的で、多様な表現や予期しないアイデアが出やすくなります。
多様性がある: 同じ質問をしても、毎回違う回答が生成されます。
Google AI StudioでGeminiを利用する際、デフォルトで「1」が設定されています。
正確な情報が欲しい場合は、0〜0.3程度が良いそうです。
以上となります。
いい利用方法や気をつけるべきことがあれば追記、もしくは新規記事あげていきます。

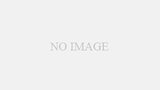
コメント